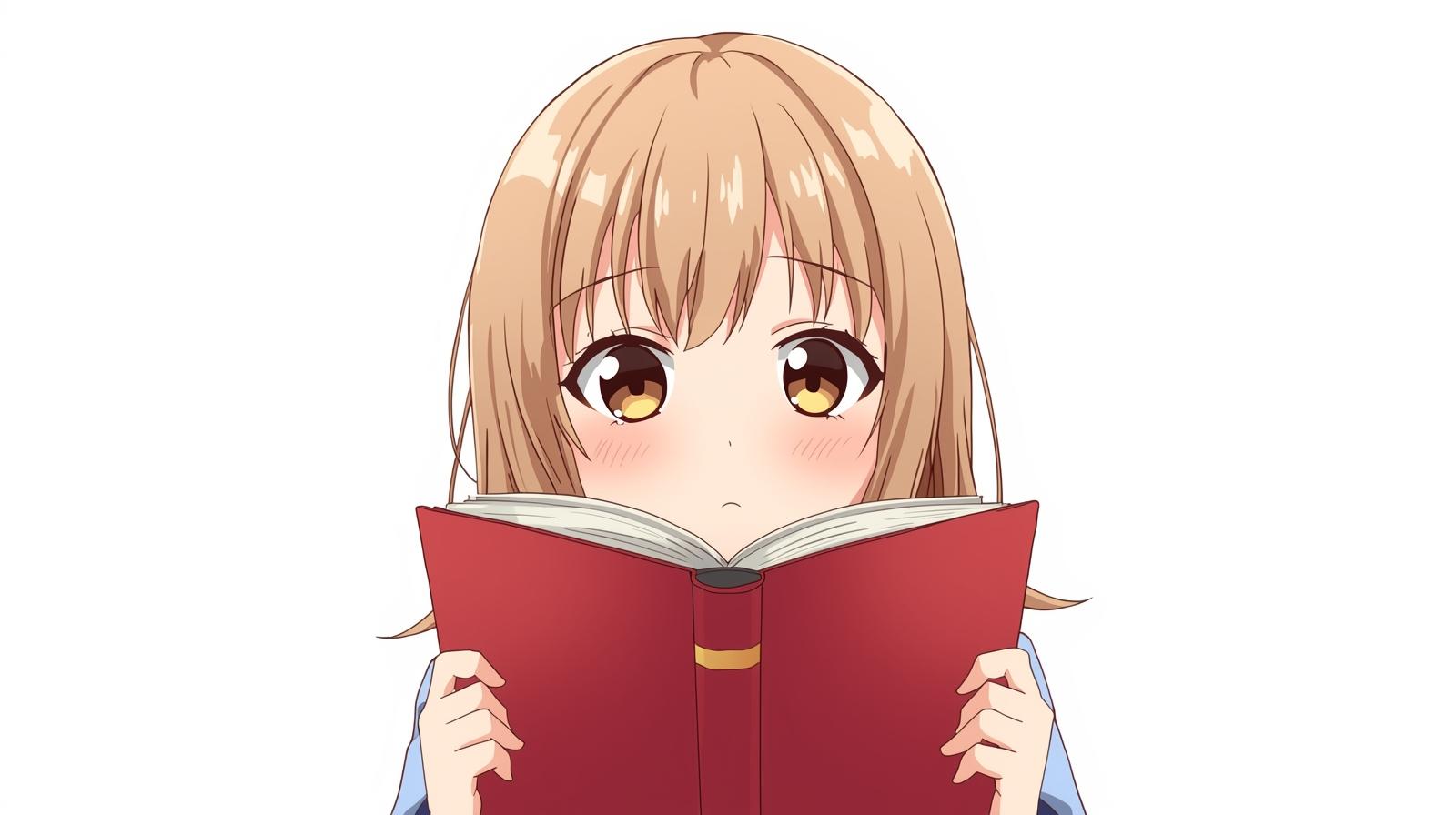【はじめに:投資信託には2つの「運用スタイル」がある】
こんにちは、「リホとミナの『安心』NISA設計室」です。
前回の記事で、NISAの主な商品である「投資信託(ファンド)」は、”投資の福袋”のようなものだと解説しました。
この「投資信託」には、その運用方針によって大きく2つの「スタイル(種類)」があります。 それが「インデックスファンド」と「アクティブファンド」です。
NISAで長期の資産形成を行う上で、この2つのスタイルの違い、特に「手数料(コスト)」の違いを理解することは、あなたの将来のリターンに直結する最も重要な知識の一つです。
この記事では、それぞれの特徴と違いを、中立的な視点で解説します。
【1.「インデックスファンド」とは?(魔法のバケツ)】
インデックスファンドは、「特定の指数(インデックス)と同じ値動き」を目指す運用スタイルの投資信託です。
- 指数(インデックス)とは?
- 日経平均株価や、アメリカのS&P500のように、市場全体の「平均点」を示すものです。
- 運用目的:
- 市場の「平均点」を上回る(勝つ)ことではなく、「平均点」とピッタリ同じ成績を取ることを目指します。(これを「パッシブ運用」とも呼びます)
- 特徴(メリット):
- 運用が「機械的・自動的」です。例えば「S&P500」という指数(レシピ)に連動させるため、そのレシピ通りに株を自動的に売買するだけです。
- 人の判断や調査が最小限で済むため、運用にかかる手数料(信託報酬)が「激安」である傾向があります。
- NISAでの例:
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
【2.「アクティブファンド」とは?(穴あきバケツ)】
アクティブファンドは、「特定の指数(インデックス)を上回る値動き」を目指す運用スタイルの投資信託です。
- 運用目的:
- 市場の「平均点」に「勝つ」こと(=平均点以上のリターン)を目指します。(これを「アクティブ運用」とも呼びます)
- 特徴(メリット・デメリット):
- 「勝つ」ために、投資のプロ(ファンドマネージャー)が独自の調査や分析を行い、これから伸びると判断した企業を選定して投資します。
- この専門的な調査や人件費がかかるため、運用にかかる手数料(信託報酬)が「割高」である傾向があります。
- プロが運用するため、市場平均を大きく上回るリターンを出す「可能性」があります。
【初心者はどちらを選ぶべきか?(中立的な比較)】
「平均を目指すインデックス」と「平均以上を目指すアクティブ」。どちらが良いのでしょうか? これは投資の世界で長く議論されているテーマですが、NISA初心者の方が判断する基準は「コスト」と「データ」です。
1. コスト(手数料)の差は「確実なマイナス」
- インデックスファンドの手数料(信託報酬):年率0.1%前後(激安)
- アクティブファンドの手数料(信託報酬):年率1%〜2%(割高)
- アクティブファンドが平均に「勝てるかどうか」は将来の「可能性」ですが、手数料がインデックスより10倍以上高いという事実は「確実」です。
- この高い手数料は、あなたがNISAで運用している間、毎日あなたの資産から引かれ続けます。(これがショート動画で伝えた「穴あきバケツ」の正体です)
2.「平均」に勝つことの難しさ(データ)
- 多くの過去のデータや研究において、「手数料(コスト)を差し引いた後」で、市場平均(インデックスファンド)に勝ち続けられるアクティブファンドは、ごく一部(例えば1〜2割)である、という結果が示されています。
- つまり、多くの「割高な手数料」を払うアクティブファンドは、結果として「激安の手数料」のインデックスファンドに負けてしまっている、というのが現実です。
【まとめ:まずは「コスト」で判断しよう】
今回は、「インデックスファンド」と「アクティブファンド」の違いについて解説しました。
- インデックスファンド:
- 「平均点」を目指す。
- 手数料が「激安」。
- アクティブファンド:
- 「平均点以上」を目指す。
- 手数料が「割高」。
NISAで「長期」の資産形成を行う場合、この「手数料(コスト)」の差が、将来のリターンに非常に大きな影響を与えます。
アクティブファンドの中にも素晴らしい商品は存在しますが、投資初心者の方が「商品選びで失敗したくない(損したくない)」と考えるのであれば、まずは「低コスト(手数料が激安)」である「インデックスファンド」から検討するのが、最も合理的かつ王道の選択と言えるでしょう。